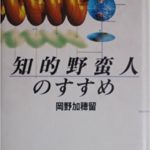以前書いた「次世代のデモクラシー」の続きです。
デモクラシーを民主政治、民主制、民主政治制度と訳すべきで、
そこに、戦後日本の民主主義の大きな落とし穴があります。
 平民宰相 原敬という政治家もいたんですが、大正10年(1921年)暗殺され、それ以降、一挙に軍国主義へ傾倒していきました。いっときの大正デモクラシーとして終わりました。
平民宰相 原敬という政治家もいたんですが、大正10年(1921年)暗殺され、それ以降、一挙に軍国主義へ傾倒していきました。いっときの大正デモクラシーとして終わりました。

日本では闘争の末に民主主義を勝ち取ってきた歴史も、歴史的な議論を巻き起こしたこともありません。
1945年、いきなり終戦を迎え、軍国主義という全体主義から、アメリカが主導した民主主義という自由主義に否応なく突入しました。それからの戦後日本は、“のほほんとしてきた日本”なのであります。
民主主義とは、主義ではなく方法論であり、手続きに過ぎません。

党大会の様子
1932年7月ナチスが国民議会に第一党となったのも、正当な選挙で絶大な指示を受けたものでした。
1933年1月ヒットラーは民主的な手続きによって大統領を兼任。これも完全なる民主主義によって選ばれました。
しかしナチス・ドイツを民主主義国家だと考える人はいません。
民主的な手続きが守られたとしても、それだけで民主的な世の中が実現される保証はどこにもありません。
さて、「日本とフランス 二つの民主主義」で、薬師院仁志は次のように言っています。
間違っても民主主義と自由主義とを同一視してはならない。
日本では、民主主義=自由主義であり、まずこの辺りから議論を説き起こさなければなりません。
民主主義には系譜があります。ひとつは自由主義、もうひとつは平等主義です。
自由主義は保守主義として、国王に代って金持ちが政権をとったもので、資本家の自由を保障する考え方です。
一方、公権力(政府)による規制によって、たとえ自由を制限してでも、平等な政策を求める考え方、これが平等主義です。
ヒーローが大好きなアメリカでは自由主義が、ヒーローが大嫌いなフランスでは平等主義が、それぞれの民主主義の原点です。
自由主義に向かえば向かうほど、規制緩和、自由化、官から民へ、小さな政府、と言った主張になります。
一方、平等主義に向かえば向かうほど、高負担・高福祉、企業の国営化、大きな政府、福祉国家といった主張が強くなっていきます。
日本の民主主義は、戦後アメリカの統治下にあって、憲法が制定されたことから、アメリカの自由主義に繋がるものでありました。ところが、自由の制限=既得権益を守ることになってしまったところに、自由か平等かといった対立図式は成り立ちませんでした。
右派=保守=反動的=統制主義であり、左派=革新=進歩的=自由主義といった、日本特異な、いびつな図式が成り立ってしまった。
トマ・ピケティーが、所得や富の不平等を問題にしているように、自由主義に乗った資本主義では、格差は拡大し、資本が世襲され、富裕層に富が集中していきます。
ソ連崩壊の後、自由主義はグローバルスタンダードのように言われています。
でもそれは違います。 自由主義だけでは、僅かな富裕層に富が集中し、貧富の格差は拡大してしまいます。
教育を受ける権利、文化的で健康に生活する権利、など社会保障の充実がなければ健全な社会はできません。

ミハエル・ゴルバチョフは振り返って語っています。
犠牲を払っても成長・発展を優先して来たことを振り返り、貧しい人々を置き去りにしてきたことに目を向けて、競争だけではなく協力し助けあうこと、人が幸せになる権利を理解し、共鳴していく社会が必要です。
自由主義であっても、平等主義であっても、社会主義であっても、イデオロギーのためにではなく「人のためにある」
民主主義であることが重要です。